東北商事の営業の軸
Central axis
二つの"ワ"
東北商事は建設資材の仕入・販売を担う商社です。生コンクリートをはじめとする地域内屈指の取扱商品数、納入案件数を誇ります。
営業の役割は、お客さま(建設会社)とメーカーの間に立ち、両者をむすぶ存在となることで、地域の建設に多くの力を呼び込むことです。そんな私たちが大切にしている、二つの“ワ”をご紹介します。
-
01
顧客•メーカー•地域と築く、
チームの“和”私たちが関わる建設という営み。
そこには多くの人びとが携わります。そこで使われる材料を届ける上でも、お客さま、メーカー、運送業者など、関係者の呼吸が重要です。
それぞれが持っている力をむすび合わせ、建設に向かう強いチームを形成する。そこに営業の役割があり、醍醐味があります。“和”のチカラが、地域の未来をつくります。 -
02
信用•信頼によって回る、
仕事の“環”営業の要は“信頼”。
私たちの仕事は契約で終わりではなく、契約通りの納品、その後のアフターフォローまであります。それによって初めて、お客さまの「品質・工期・採算」が実現されます。
お客さまやメーカーとの協議を重ね、プロジェクトが完成に至った時、信用や信頼という得難いものが積み上がります。その無形の財産は、次のプロジェクトでの営業の原動力となり、より強いチームの形成にも繋がっていくのです。
東北商事の
営業の仲間
Interview
東北商事の営業メンバ―、グループ内の仲間、取引先の方々、様々な視点から見た「東北商事の営業」の姿をお伝えします。
営業メンバー
東北商事で働く営業メンバーにインタビュー。
「営業の仕事とは?」経験豊富なメンバーに、普段はなかなか聞けない想いまでとことん聞いてみました。
-
 member 01
member 01人とのつながりで、地域を支える
東北商事株式会社
常務取締役
半谷 真司
-
 member 02
member 02地域の未来を、かたちにする営業とは?
東北商事株式会社
営業次長
村澤 典洋
-
 member 03
member 03「あなただから頼みたい」の一言を引き出すために
東北商事株式会社
営業課長
二本松 賢治
グループ会社内対談
インタビュー
いつも営業メンバーの近くにいるグループ社員3人で、
「一緒に働いているからこそ見えている東北商事の営業」について語りました。
-
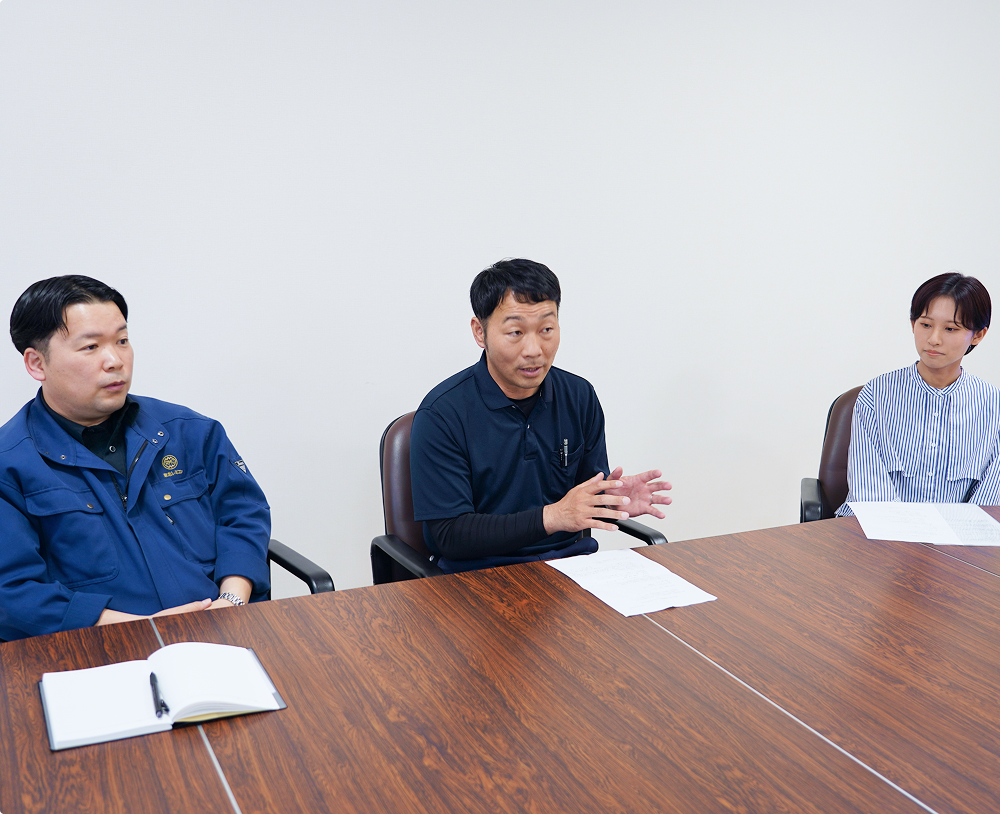
一丸となって、想いに応える
-
東北レミコン株式会社 原町工場
品質管理課長
三浦 友和
-
東北レミコン株式会社 相馬工場
品質管理課長
渡邉 恵次
-
東北商事株式会社
総務部主任
竹林 真由
cross talk
-
社外インタビュー
「取引先の方々から見る東北商事の営業」について語っていただきました。
-

地域から強く信頼され、一緒に仕事をつくるパートナー
-
株式会社フソウ
営業本部 東日本営業部 係長
定野 敬史様
interview 01
-
-

「そうだ、東北商事さんに聞いてみよう」と思える存在
-
日鉄物産株式会社
東北支店 建材課
蕪木 翔太郎様
interview 02
-
営業の仕事~事例紹介~
Projects
私たちが実際に携わったプロジェクトをご紹介します。 それぞれの事例が語るのは、私たちが営業活動する舞台そのものの魅力です。
営業メンバーmember 01
人とのつながりで、地域を支える
東北商事株式会社
常務取締役
半谷 真司
まず、営業という仕事を始められたきっかけをお聞かせください。学生時代は高校球児で、甲子園まで行かれたと事前情報を伺っています。
たしかに高校球児ではありましたが、高校2年の時に補欠で甲子園に行って最後に代打で出してもらっただけで(笑)
そのあと半分 野球推薦みたいな形で大学に進み、一応長男ということもあって、地元に戻って知り合いのつながりで入社しました。最初は東北レミコンに総務みたいな形で入ったのですが、向いてなかったのか東北商事の営業に回って…(笑)
40年近く月日が経ちました。
営業のお仕事の中で、取引先と関わる上で大切にされていることを教えてください。
やはり、互いに信頼できる関係性ですね。納期を含めてお客様に対する約束事は厳守しなくてはならないので、そこはメーカーにも協力をお願いする形で信頼関係を築いています。
私が思うには、仕事の大小にかかわらず、誠心誠意いただいた仕事を完遂させること。最終的にはそれが長続きする何よりのポイントなのかな、と。
工事期間が予定通りにいかないなど、臨機応変な対応も多い中で、そうした関係作りやコミュニケーションも必要ですね。
間に入っている商社の立ち位置としては、潤滑油のようにスムーズな流れを作るのが重要な仕事の1つかと思います。 ただ単に物を流すだけにならないよう、なるべく気持ち・心遣いを添えるようにしています。
営業マンとしてのキャリアの中で「これは転機だった」「忘れられない現場だ」と思う出来事はありますか?
20代で営業になって、独り立ちというか、一人でお客様のところをまわるようになって、初めて大型物件を受注した時のあの嬉しさ、充実感は今でもよく覚えています。あとは東日本大震災時の復旧工事の経験は大きかったですね。
初めての受注はどのような部分が印象的でしたか?
通常うちから生コンクリートを購入されないお客様のところに何度も通ったんです。そして相手の社長から最終的な返事をいただいて成約したときの気持ちは今でも深く心に残っています。
![]()
震災の時のお話を伺えますか?以前のインタビューでは受注量も膨大でとても忙しかったと聞いております。
復旧工事が本格化してからは本当に大変でした。
通常であれば10~20キロくらい離れた山から生コンクリートの骨材をとってくるのですが、原発事故の影響で閉鎖してしまった採石場もあったため、山口県や北海道から船で運んできた材料を使うなど、仕入先経由で探してもらって必要な分をなんとか確保していました。
社員やその家族、取引先の方々も被災している状況で、何とかやりくりしていたという感じだったと思います。
そんな中でも、大きく壊れた地域のインフラを復旧させていかなければならないという状況もありましたし、当時社長から「みんな大変だとは思うが、同じく大変な地域のために、少しでも仕事で役立っていこう」と励まされていたので、その思いで頑張っていました。
東北商事の営業としての面白さは、どんなところに感じていらっしゃいますか?
商談が成立して、お互いに納得した形となるのがベストですが、そこを目指して相手との距離感を掴んでいく面白さがあると思います。
抽象的な話になりますけど、人と人との関係は簡単なようで、やはり難しい。近づきすぎても、離れすぎても…という感覚があって、 その距離感は相手によっても変わってきますし、自分の感性の中で養っていくものだと思っています。
あとは、建設工事における構造物が出来上がる過程でいろいろ携わらせていただいているので、実際に街で建物や道路を目にして、「あの時こうだったな」と思い出が蘇ることも面白さの1つですね。長い間かたちに残るものですので、同時に責任感や達成感も湧き上がってきます。
幅広い建設資材を取り扱われているからこそ、納期や納品場所の調整といった部分で、ちょっとドキドキするようなこともあるんでしょうか?
そうですね、ありますよ。
例えば、メーカーから「1カ月かかる」という回答に対して、現場は「20日間で納品してもらわないと困るよ」っていう場合もあって、間に入って調整する場面は多々あります。そこでの対応によって人間関係も変わりますし、もし変われば充実感もあります。
調整に失敗してしまい、「あなたのところからはもう買わない!」と言われた経験もあります。それでも、諦めずにそこから関係を修復していくことも大事な仕事だと思うようになりました。難しいところであると同時に、真価が問われるところでもあると思っています。
最後に、これから仲間になる人へのメッセージをお願いします。
やはり、「地域の役に立てている」という気持ちを持てることが、長い目で見たら一番のモチベーションかと思います。
我々の仕事においては、地域とのつながりやそれに対する役目のようなものを感じながらやってきました。大震災の復旧工事を通じてもそれは強く実感した部分です。
これから新たな建設プロジェクトとして、学園都市のような国家規模の構想も実際に動き出してきているので、そういった未来に向けたプロジェクトをこれからの人たちに担ってもらいたいと思っています。
会社である以上、数値目標はもちろんありますが、それが先に立ってしまうと、空回りする場面もある気がします。
人とのつながりや、地域の役に立とうという思いを脇に置いてしまって、自分たちの都合だけで動いてしまうと、結局はつまずいてしまうんじゃないのか?と思います。かといって数字を抜きにして、やりたいようにやるわけにもいきませんので、うまくバランスをとりながら面白がってやってもらえればと思います。
![]()
営業メンバーmember 02
地域の未来を、かたちにする営業とは?
東北商事株式会社
営業次長
村澤 典洋
営業の仕事を始められたきっかけを教えてください。
元々は技術系で、宮城県でヨットやモーターボート、漁船・遊覧船などのエンジン修理といったことをしていました。結婚を機に地元に戻り、社員の紹介で東北レミコンに入りました。旧小高工場と旧双葉工場に1年ずつくらいいまして、製造、品質管理、忙しいときは輸送と三刀流でした(笑)
入社して数年目のある日、工場次長から「社長のところに行ってきて」と言われ、どういう訳か突然「これからは営業として頑張って下さい」と言われて始まったがきっかけです(笑)
当初はすごく戸惑いましたね。営業の経験は全くなかったので、まず何をしたらいいのかもわかりませんでした。同郷の半谷常務が既に営業にいたので話を聞きながら、あとは自分の親くらいの年代の先輩から教わりながら、いろいろ試行錯誤してなんだかんだやってきました。
なんだかんだにしてはとても長く続けられていますが、続けられた要因は何でしょうか?
あんまり考えたことないのですが…人と話をしたり、自分で営業して仕事が取れたりすることが励みになったところはあったかなと。
あとはやはり、東北商事という地域で名の通っている会社の社員だというのも大きかったと思います。私個人の力だけではなくて、お客さんにも「東北商事」という名のおかげで話を聞いてもらえたり、仕事をいただけたと思っています。
日常的に現場とのやり取りが多いのですね?
そうですね、密に連携しています。現場の監督さんも忙しいと、資材の注文を忘れることがあるんです。
生コンクリートの注文を忘れて、「今日現場で使いたいんだけど何とかならないか?」という飛び込みの連絡を受けることもあります。全部が全部、解決できるわけでは当然ないのですが、それに対していかに応えるかが大切だと思っています。うちにはグループの生コンクリート工場がありますし、他の資材がない時には問合せできる仕入先をいろいろ当たるなどして、できる限り現場に間に合わせるよう努力します。
普段からの仕入先との関係性は、そういう時ほど大事になります。計画的に打ち合わせしておければ一番ですが、お客さまの緊急時に「間に合いません」の一言で済ませるわけにはいきませんので。
私たちが実質的に関わるのは資材を納品するところまでですが、本当は施工して気持ちよく使っていただくまでが自分たちのゴールだと思っています。
困った時に、声をかけてもらえる存在であるというのは重要ですね。
そうですね。もちろん何社かに声をかけるケースもあるんでしょうが、真っ先に連絡をいただけるような存在でありたいと思っています。
![]()
今までの経験の中で「忘れられない現場・出来事」を教えていただけますか?
いっぱいありすぎて…(笑)
それでも、東日本大震災の時を一番思い出しますね。
当時自宅が避難区域の20km圏内に入ってしまったので、会社を離れて宮城県まで避難していました。ライフラインも寸断され、おそらくもう元の暮らしには戻れないかなと思いながらサバイバルのような生活をしていた時に、半谷常務から連絡があって。「お客さんから生コン欲しいって話が来始めたけど、村澤さんは今はどんな状況?」と。
相馬工場は避難区域外だったので、震災直後から稼働できる状況でした。住む場所も見つかっていない状態でしたが、何か力になりたいと思って仕事に復帰しました。
もともと生コン車の運転はできたので、まずは必要とする現場に運ぶことから始めました。社員の多くが被災したことで、震災直後はドライバーの手が足りなかったのです。
テトラポットに代表されるコンクリートブロックを海に並べていかないと堤防復旧も進まないので、毎日大量の生コンクリートを運びました。自社の車だけでは供給が間に合わなかったので、北海道などの遠方からも車両を借りて対応していました。
あの時は使命感というのかな、なんて言えばいいのかわからないのですが…私たちだけでなく、現場の人たちも被災している中で、とにかく「各々が出来る行動をしていく」という想いがみんなにあったと思います。
地域とのつながりはどんなところで感じられますか?
子供が小さい頃に一緒に出かけたりすると、生コン車が街を走っているのを見て「お父さんの会社の車だ!」って言われたりとか。あとは、この橋やこの水路に「お父さんが納めた材料が使われている」って言えるのは良いですよね。かたちとして残るので。
私たちはものを納めるのが役割ですけど、それを現場で形にしてくださる方々がいないと完成とはならない。少し大げさかもしれないですが、建設業そのものが地域を支えていて、その一端を自分たちが担っているのだと思います。
「東北商事の営業を取り巻く環境」はどのように変わってきたとお感じですか?
働く人たちの世代が変わってきていますね。最初にお世話になった方々は、その多くが引退されています。
震災後には、もともと地元に拠点がない会社が営業所を構えるようにもなり、競争も進んできました。そうした中でも選んでもらうためにはどうするのか、ということが重要になってきています。
今、現場の仕事を仕上げるには「東北商事に頼むのが一番だ」と思ってもらう。「値段+α」をどこまで感じていただけるかだと思っています。
そうするとやはり現場とのつながりも欠かせませんね?
だからこそ、早めに情報を取って、設計書をもとに必要な資材を洗い出すことが大切です。後から変更になることもあるので、現場に顔を出しながらその時々の状況を掴んでおくことも欠かせません。
仕事の中で関わる担当者の方々も、世代交代されて変わってきています。そこをうまい具合につないでいかないといけないんです。営業にはそういうつながりの連鎖を作っていく使命があるということでしょうか。
そこが難しいところでもあり、やりがいでもあります。
これから新しく仲間になる若手のために、どんなことを心がけていきたいですか?
私自身、会社の先輩方によって「東北商事の村澤という存在」をお客様とのつながりの輪に加えていただいたからこそ、今の自分があると思っています。今度は自分が後輩へうまくつないでいくこと。これが、自分のやるべきことだと思っています。
![]()
営業メンバーmember 03
「あなただから頼みたい」の一言を引き出すために
東北商事株式会社
営業課長
二本松 賢治
営業という仕事に就かれたきっかけをお聞かせください。
最初は東北レミコンに入社して、17年間、工場勤務でした。品質管理の業務がメインで、合間に出荷業務、製造業務など、ひと通りこなしてきました。
そんな中、平成17年に東北レミコンから東北商事の営業に異動となり、今日に至ります。最初は驚きましたが、「他の人たちがこなしているのであれば」という思いで始まりました。
お仕事の内容もかなり変わったと思いますが?
全く別物だと感じます。ましてや今度は人相手なので、そのあたりの神経はだいぶ使いますね。
営業の仕事は、「人対人」。それに尽きると思っています。どこに、誰にアプローチしていくのか、その順番一つ間違えるとマイナスになってしまうこともあるので、きちんと筋を通して進めていく感じです。それは教えてもらうだけではなくて、ある程度自分で足を運んで、「ここの会社はこういう感じなんだな」と肌で雰囲気を掴み、そこに自分を合わせていくことが必要かと。お客様ごとにカラーがありますし、人も違うので、それが重要だと思います。
忘れられない現場・出来事があれば教えていただけますか?
私が営業になりたての時に、山腹の地すべり対策工事がありました。大きな規模の案件だったんですが、もともと想定されていた設計内容と現場の実情にズレが生じておりまして…。特殊な資材も使っている中で、当初の想定よりも大分多くの費用が掛かったのですが、本来ならそうなる可能性も慎重に考慮した上で仕事を進めていかなければならなかったんです。
最終的には協力を依頼した施工業者に何とか現場を仕上げてもらったのですが、それでも結果的にお金が足りなくなり、仕入先にも迷惑を掛けてしまったという出来事で、今となっては私の営業のいい教材となっています。
それは面食らう出来事ですね…!
もうクラクラしました(苦笑)工事が始まってから「設計と現場の状況が違うんじゃない…?」という話になって。営業になって1,2年目の出来事でしたが、そのあたりの知識が十分ではなく、仕入先に頼っての現場対応となってしまいました。
その仕入先には助けてもらった恩義があるので、「今後は少しでもお返しできる仕事をつくっていこう」と強く思ったのを覚えています。
そういういろんな経験や失敗をしながら、少しずつ仕事の質が上がってきたのかなと思っています。触れたことのないような新しい仕事・案件でも、ある程度自分のイメージをもって挑戦できるようになってきたと思います。
見積や積算、現場の状況、進める仕事の内容も「こんなイメージだろう」というのを自分の頭の中で組み立てていけるようになった感じです。まあ、外れることもあるんですけど(笑)
![]()
そうなれるまでに、どれくらいの期間かかりましたか?
極端に言うとここ最近になってからかもしれません。
土木と建築にまたがるので、扱う資材は多岐にわたります。最初から深い知識を持つというよりは、広く知っておくことが大事です。全部が全部、深くは頭に詰め込めないので。
その中でポイントをつかんでお客様といろいろ話をしながら、求められている部分を関係者と一緒に深めていく感じです。
日頃、「腕の見せどころだ」と感じられる部分はどんな場面ですか?
契約通りに仕入先に納品の依頼をしても、ごくたまに違ったものが入ってしまうことがあるんです。どこかで認識がズレてしまって、現場から連絡が来る。間違えたのはどこか別のところですが、お客様の窓口は私なので、まずは「すみません」と謝ります。そこからどこでどう間違ったのかを調べ、大急ぎで正しい資材をもう一度納める・・というのはあるあるですね。
こうした時ほど、営業としての対応が問われると思います。
確かに、そういうことは起こり得ますね。工事スケジュールの変更なども多いと思いますが、そういう調整を円滑に行うためにもどんなことを大切にされていますか?
関係先との信頼関係を長い期間で築いておく必要があると思います。お客様のところに行って、顔馴染みになって座ってお茶でも飲みながら、ちょっと濃い話ができるようになるまでは、やっぱり時間はかかります。それでも、最初は立ち話をしていたのが、中に通してもらって段々といろいろな話ができるようになる。
その時にはどんなお話をされるのですか?
仕事の話も当然それなりにしますが、世間話のほうが長くなることもあります。堅苦しいだけでも良くないですし、その人が興味ありそうな話をしてみたり。
私が良かったなと思っているのは、17年間の工場勤務時代に、品質管理として現場にも出入りしていた関係で、顔見知りの方々が結構いました。そのため、自然体で営業の仕事にも馴染んでいけたと思います。
営業になられて、地域や社会に対する見方にも影響がありましたか?
そうですね、自分たちの仕事が地域に与えている影響により気づくようになった感じはあります。インフラ整備は然り、住宅を建てる時も生コンクリートを使いますので、私たちの材料が多かれ少なかれ地域に役立っているんじゃないかなって思います。
街を走っていると、思い出の場所じゃないですが、「あそこの現場にも関わったな」と当時を思い出すことがあります。
工場にいた時はコンクリートのことだけを気にしていましたが、東北商事に来てからは構造物を見ると勝手に3Dで「この中に入っているこれとこれとこの資材はうちで納品したな」という感じで見るようになりました(笑)
お仕事の中で大切にされている価値観やお考えはありますか?
お客さんに「またこの人に頼みたいな」と思ってもらえる仕事をするようには心がけています。それはずっと変わりません。
この業界は一本気な方々が多いので、その人たちに対して「資材を売るだけでなく、自分自身を買ってもらおう(=信頼してもらおう)」っていう気概が大事だと思います。
実際に期限が短いお仕事も多いですよね?
そうですね、納品に緊急を要することが結構あります。本当は「もう少し早めにお願いします」と思う時もありますが(笑)
お客様が困っている時、緊急の時はギアを一段二段上げて、あらゆる対応が取れるようにしようという心構えでいます。
そんな経験をたくさんしてきたので、どんな仕事が来ても少しのことでは驚かないし、自分のイメージで対応して仕上げていけば、喜んでもらえて信頼に繋がっていくものだと思っています。
営業という仕事の中で、自分自身が一番成長できたと思うのはどんな点ですか?
人との話を楽しむようになったと思います。いろいろな情報を頭の中で整理しながら、相手は本当は何を望んでいるのかな、とか。
相手の考えを要所要所でつかむ。時には性格までもつかむ必要があります。お客様に合わせた営業、これが一番大事かと。いただいた仕事に向き合って、いい意味でサプライズができるよう、そして喜んでもらえるように、と常々考えています。
![]()
対談インタビューcross talk
一丸となって、想いに応える
-
東北レミコン株式会社 原町工場
品質管理課長
三浦 友和
-
東北レミコン株式会社 相馬工場
品質管理課長
渡邉 恵次
-
東北商事株式会社
総務部主任
竹林 真由
まず皆さんの自己紹介と併せて、担当業務や、普段どのように営業の方々と関わっているのか教えていただけますでしょうか?
渡邊:相馬工場 品質管理課長の渡邉です。営業のメンバーとの関わりで言うと、お客様との会話の中からいろいろな要望を受け止めたものを伝えに来てくれ、その内容を共有して仕事を進めていくという感じですね。
三浦:原町工場 品質管理課長の三浦です。渡邉君と仕事内容は同じですが、営業メンバーに同行し、一緒に現場打ち合わせすることもあります。そこでは、お客様からご要望いただいた内容の擦り合わせなどを実施します。
竹林:東北商事 総務部主任の竹林です。営業メンバーのもらった書類から伝票を起こしたり、電話対応や請求書の作成などがメインです。その中で、担当者と認識のずれがないように、わからない事があればその都度相談するようにしています。
営業メンバーの皆さんはベテランの方が多いですが、普段はフランクにお話しされますか?
全員:そうですね。
営業の3人はタイプがそれぞれ違いますよね?
三浦:そうですね、結構違いますよ(笑)
渡邉:だからこそ、全体でうまく回るのかもしれません。
竹林:それぞれの個性はありますが、皆さんに温かく接していただいています。世代的に自分の父親に近いので、本当に家族みたいな感じです。
![]()
営業の現場と連携する中で、印象に残っているやり取りや出来事はありますか?
三浦:震災があったとき、営業の皆さんが力を貸してくれて。復旧工事の仕事が結構あって、生コン車を運転する人手がどうしても足りないことがあったのですが、みんな大型免許を持っており、運搬を手伝ってもらった時期がありました。あの時は東北商事も東北レミコンも一体となって一生懸命やったという印象が本当に強く残っています。
渡邉:震災対応では、みんなが一丸となってやりましたね。「何とかしないと」という想いで必死にやっていました。あれでみんなの距離が縮まった気がします。震災の前後で会社の雰囲気はかなり変わりました。
三浦:本当にそうですね。それまで東北商事と東北レミコンは別のところにあったのですが、震災がきっかけで東北商事が東北レミコン相馬工場に間借りする形で一緒の敷地内となり、それも距離が縮まった要因の一つかもしれません。
竹林:私は震災後の入社なので、そういう大変だった時のお話を聞くと皆さん支え合いながら頑張ってこられたんだなと感じます。
普段、営業の方とはどのくらいの頻度で会話されるのですか?
渡邉:毎日というわけではないですが、近くを通ったときに顔を出してくれて、仕事の話をいろいろしてっていう感じですね。
竹林:やはり営業の方は外に出られていることが多いので、朝と夕方それぞれの時間帯で、仕事を進めていく上での確認などを話し合っています。
東北商事と東北レミコンが2社で一緒にやっているからこその想いや出来事があるのかなと思うのですが、いかがでしょうか?
渡邉:2社で一緒にやっているからこその強みがあると思います。東北商事と東北レミコンがそれぞれの役割を果たすことで、お互いの力になっているという感覚が大いにあります。
三浦:その通りだと思います。
ところで、生コンクリートはとでも繊細な材料なので、結構工夫が必要なんです。天気や気温によっても性状が変わりますし、運ぶ距離によってもコンクリートの配合を修正したりして、ベストな状態で現場に届くようにします。
営業の方々が苦労して取ってきてくれた案件ですので、「今回の注文は、品質面や運搬面で相当骨が折れそうだな」と感じることがあっても、できる限りのことをして応えようと思っています。
![]()
新しい営業さんが仲間になるとしたら、皆さんどんな人に来てほしいと思いますか?
渡邉:精神力のある人ですね。緊急で対応しないといけないこともあるので、そこに対応できるのは大事だと思います。
それはパッとすぐに動ける瞬発力みたいな感じですか?
三浦:それもですが、自分としては柔軟さの方かな。
渡邉:確かに、周りの状況を把握・整理しつつ、そこに合わせるために考えながら動ける人だといいのかも。
あとは、コミュニケーションを取りながら一緒にやっていきたいですね。一人では絶対に回らない仕事なので。竹林さんはどう思いますか??
竹林:そうですね…生コンクリート以外にもいろんな建設資材を扱うので、知らない分野にも興味・関心をもって取り組んでいける人がいいのかなと思います。
最後に、これから仲間になる人へ向けて、メッセージをお願いします!
竹林:営業の皆さんは本当に優しくて、とても働きやすい環境です。これから来ていただける方とも支え合いながら、困ったときも手を差し伸べ合って仕事ができる環境を作っていきたいと思います。
三浦:仕事としてはタフな案件もあったりしますが、そこは皆でカバーし合いながら共に成長できればと思っています。社内は年齢差もありますが、そんなことは気にならないくらい話しやすい環境なので、一緒に頑張っていけたら嬉しいです。
渡邉:どんどん輪の中に入ってきてくれると嬉しいですね。東北商事、東北レミコン問わず、仲間として飛び込んできてくれる人が長く続けられるのかなと思います!
社外インタビューinterviews 01
地域から強く信頼され、一緒に仕事をつくるパートナー
株式会社フソウ
営業本部 東日本営業部 係長
定野 敬史様
定野様は今年の4月まで、クボタグループの資材を卸す窓口の、フソウ東北支店の担当として長く東北商事と関係を築かれてきたと伺いました。
はい、丸8年担当させていただきました。東北商事さんは本当に自分を育ててくださった会社の筆頭だと思っています。新入社員で正配属として赴任した時からお世話になって、20代はずっと一緒に仕事させていただきました。
弊社は農業用水のパイプラインの管材を主に取り扱っていまして、東日本大震災後の農地再生事業が始まった頃に私は入社しました。
長いお付き合いということで、東北商事の営業メンバーのそれぞれの印象を伺ってもいいでしょうか?
半谷常務はやはり頼れる存在というか、兄貴肌の方です。営業の責任者という形で、後ろから見守ってくれています。経歴もすごく長いので、福島の浜通りというエリアを一番広い視野で見ている方だと思っています。自分も本当に甘えさせていただいて、最初は至らない部分も多くてご指導もいただきながら、いい関係でお付き合いさせていただいたと思っています。
村澤次長は、最初の頃はあまり口数が多い方というイメージではなかったのですが、お客様に対する思いやり、熱い想いを強く持っている方です。意見が異なることがあっても、お互いがお客様のことを想って話をすることで、最終的にはいつも同じベクトルで営業活動できる仲間でした。
二本松課長は、お客様との連携でも何でも、とにかく圧倒的なスピードでリアクションをくださるので、それがすごく自分の成長につながりました。情報の鮮度も高いし、温度感も伝わる状態で届けてくれるので、相手の生の声を聞き取るのがすごく上手な方なのかなと思っています。
タイプとしては勇猛果敢というか、お客様の方にまっすぐ突き進んでいく営業マンという印象です。
三者三様の個性があるからこそ、地域の幅広い建設会社の方々から信頼されているのかなと思います。
![]()
東北商事の営業メンバーの頼れるところはどんな部分だと感じますか?
レスポンスがとても早いところですね。キャッチボールが本当に早くできるので、お客様のリアクションを薄めない。やはり、メーカーはお客様と少し距離のある立場なので、そういったところがなかなか聞き取りづらくて要望に応えられないことがあります。でも、東北商事さんからは本当にすぐ連絡をいただけるので、こちらもすぐリアクションできる。
仕事をつくるのが一番の目的なので、ここまで一緒に前のめりになってくれる仲間がいるんだと思えるのがすごく嬉しくて、私としてもそれ以上に応えなければならないと思います。
東北商事の営業メンバーの「お客さまへの向き合い方」で特徴的だと感じる部分があれば教えてください。
私の感覚で言うと、「お客様と商社」という関係性ではないところですね。一緒にひとつの現場を作り上げるためには、東北商事さんがお客様から必要とされているからこそ、社員・パートナーみたいに「この人に言えば大丈夫」と思ってもらえる間柄になっているように思います。
東北商事とのやり取りの中で、特に記憶に残っている出来事はありますか?
最初衝撃を受けたのは、東北商事さんと一緒に同行させていただいた際に、お客様の方から「もう、これは東北商事さんにお願いするからね」と見積提出後、早々に決まる案件があったことですね。
もちろん、見積提出以前から営業されていたからだとは思うのですが、「東北商事さんだから」と言われるくらい信頼されているお客様もいらっしゃるので、そこがかなり衝撃でした。ロイヤリティーの高いお客さんを3人が全員ともしっかり持っていらっしゃるので、そこがまたすごいと思います。
個々の営業マンとしても、また東北商事という会社としても、二重の意味で任せたいと思われていることがすごいですね。業者さんと信頼関係ができていて、プロジェクトの状況を事前に共有できているからこそなのかなと思っています。
東北商事の営業の、強みや特徴はどこにあるとお感じですか?
仕入先と売先って、「買っていただいている」という関係性が一般的だと思うのですが、東北商事さんは仕入先も対等な目で見てくれる。そういう風通しの良さがあります。
営業メンバーが私の手綱を握ってくれていて、「今回は俺1人で行ってくるから」「今回はアポ取らずに別の話のタイミングで聞いてくるから」などと細やかな調整をしてくださるので、本当に頼りにさせていただきました。
会社全体として、東北商事の特徴や魅力をどのように見ていますか?
一番は誠実さと実直さだと思います。お客様だけにではなく、仕入側も含めた取引先各社に対して、そういった姿勢は確実に響いていると思います。
![]()
最後に、今後、東北商事に期待することや、新しく営業の仲間になる方に向けたメッセージをお願いします。
地域に長く根差した会社であり、その自負を持って働かれている方々がいるのが東北商事さんだと思っています。
そのスピリッツを持って一緒に挑戦できる人が来てくれれば、すごくいいなと。あれだけの経験を持っている人たちからバトンを受け取るのは大きなやりがいだと思いますし、新しいものに果敢に取り組める好奇心と向上心を持った方であれば、大丈夫だと思います。
今いらっしゃるメンバーもチャレンジャーなんでしょうか?
皆さんそうだと思います。環境条件が毎回異なる中で、情報を果敢に取りに行って市場を作り上げてきたチャレンジ精神のある方々です。
会社として強固な基盤があるので、これからも次世代の人たちがいろいろな挑戦をされることで、東北商事さんを更に飛躍させていくことができるのかなと思います。
社外インタビューinterviews 02
「そうだ、東北商事さんに聞いてみよう」と思える存在
日鉄物産株式会社
東北支店 建材課
蕪木 翔太郎様
日頃、東北商事の営業メンバーとやり取りをされていて、どんな印象をお持ちですか?
皆さん雰囲気はそれぞれ違いますが、常々感じるのは、共通して「お客様との信頼関係が相当あるんだな」ということです。
私自身は昨年4月に赴任しまして、そこから鉄筋や日本製鉄グループ製品などの鋼材を東北商事さんに納品する窓口として関わらせていただいています。
価格から納品先への営業方法までをいろいろお話しさせていただく中で皆さん、責任感がすごく強いなと思っています。
営業メンバーのどんなところが「頼れる」「信頼できる」と感じますか?
一緒に地元のお客様へ伺ったとき、その方たちと同じくらい地元への愛情というんですかね、そういうものを持たれてお話をされていました。そういう部分が信頼につながっているのかなと思います。
あとは、対応がとても早いところですね。何かご依頼すると、すごく丁寧に調べてくださった上で、すぐにお返事をいただけるのでとても安心感があります。一緒にお客様のところに行ってもやはり、聞かれたことに対してすぐに回答されているので、そういったひとつひとつのレスポンスの早さが信頼関係に繋がっているのだと感じます。
東北商事とのやり取りの中で、特に記憶に残っている出来事はありますか?
今年受注できた大型案件ですね。
一番最初に東北商事さんから情報を聞いたのが、昨年の秋か冬でした。そして今年に入って具体的に「こういう大きい案件が来る」という連絡をいただきました。通常だと別のルートが強い案件だったのですが、早い段階で東北商事さんから「ぜひ(案件を)取りたい」とお話をいただき、営業方針なども含めて打ち合わせを進めていました。情報収集が早く、当初から色々と連携いただいていたので、メーカーとの協議などの準備期間を十分に確保することができました。トータルだと半年くらいの営業期間があった中で最終的に受注することができ、私自身とても嬉しかったですし、すごく強く印象に残っています。
この案件に限らないのですが、東北商事さんは相双地区の情報をキャッチするのが本当に早く、スタート時点から細やかに連携していただけるのがすごくありがたいです。
皆さんとは経験値も全然違うのに、私の意見もよく聞いてくださりますし、同じ目線で、相談ベースでお話しできるのもとても助かっています。
「こういう案件があって受注したいんだけど、どうしたらいいかな?」と頼っていただけるからこそ、それに応えたいと思っています。
![]()
東北商事の営業メンバーの強みや特徴はどこにあるとお感じですか?
「頼んだ以上は受注するんだ」っていう想いの強さと責任感ですね。お互いに意見を言ってWin-Winになれる関係を築けるように気を遣っていただいているように感じますし、営業に同行した先でお会いする地元のお客様を見ていても、「これは東北商事さんだから話してくれている内容だな」というケースがよくあります。
私が皆さんとお仕事をご一緒させていただくようになってから現在1年半ほどになりますが、いちばん最初の印象としては…正直言うと、ちょっと怖かったです(笑)。営業メンバーの方々も、年齢の離れた若い私がいきなり担当として伺ったので、お互い探り探りなところはあったのかなと。
最初はお電話でのやり取りが多かったのですが、やはりきちんと顔を見てお話ししようと思って直接伺うようにもしました。今では毎回しっかりと意見交換させていただいている実感があります。
東北商事の特徴や魅力をどのように見ていますか?
東北商事さんに相双地方の案件のことを聞けば大体はわかると思えるような情報力、あとはコミュニティの広さ、代々つながっている強固な信頼関係、この3つが魅力であり強みだと思っています。
東北商事さんとしてのブランドもあると思うのですが、それと同じくらい営業の方々が個々人で取引先との関係性を築かれているのも強さの要因なのかなと思います。
![]()
最後に、今後の東北商事、そして営業のメンバーに向けたメッセージがあればお願いします。
日本製鉄グループとしての強みを活かしながら、東北商事さんと一緒に0→1をつくっていくことを実現できれば、すごくやりがいや達成感があります。
東北商事さんのお客様に対し、新たな鉄の品種を提案していくなど、一緒に未知の分野にチャレンジできればと思っています。
まずは、私自身が今以上に営業の皆さんから信頼を得る努力をして、社内外のいろいろな場で「日鉄物産の蕪木」の名前を挙げていただけるくらいの存在になりたいです!
復興の軌跡を支えた“鉄の力”と“人の想い”
事例紹介projects 01
- 相馬港港湾災害復旧工事(岸壁)
- 鋼矢板(日本製鉄)
震災と、港の復興への想い
令和3年(2021年)、令和4年(2022年)と2年連続で震度6強の地震に見舞われた相馬港。小名浜港に次ぐ福島第2の港である。火力発電所が近く、石炭、LNGをはじめとした産業に使われる物資が日本のみならず世界中から届けられる。
しかし、この地震によって港全体が被災。一部では船が接岸できなくなってしまった。
地域経済・産業の要である相馬港の復旧工事は急務。行政も地震発生直後から対応に動いていた。
資源が届かないことによる地域産業への影響は大きい。それは東北商事・東北レミコンにとっても例外ではない。
生コンクリートを作るのに必要なセメントは、大船渡や北海道から相馬港にあるセメントメーカーのサービスステーションに船で運ばれ、そこから東北レミコンの工場へ陸上輸送されてくる。
実は、この相馬港のサービスステーションを誘致した一人が、創業者の佐藤十郎であった。縁の深い港の復旧プロジェクトには、「東北商事としての役割を果たしたい」という想いがことのほか強かった。
![]()
鉄の力、人の力
今回、東北商事が納品することとなり、本プロジェクトの要となった鋼材は「鋼矢板」。土留めや止水のために用いられる、凹凸状に成形された鋼板で、組み合わせて岸壁などの場所に鉄の壁を作る用途で使われる。
厚さはおよそ10~20mm。その薄さで岸壁の土砂を全て受け止める。そんな鋼矢板は、東北商事の主力商材のひとつである。
製造元の鉄鋼メーカーグループとは創業以来の取引関係。お客様(建設会社)からの依頼内容や、現場の状況、物件情報などを、メーカーに足を運んで密に連携し、「予算や納期をはじめとする情報の共有」や「メーカーの協力取り付けの調整」に力を注いだ。
復旧工事は、時間との闘いである。正確な設計・図面をもとにして工事発注する手順を踏めないケースもある。測量しつつ、その状況に応じて必要な鋼矢板の枚数、加工条件などを算出し、現在進行形で決定しながら進めていく。
鋼矢板は長さから塗装までがオーダーメイドの受注生産品であり、在庫はない。製造タイミングを1日でも逃すと納期が1か月延びてしまうこともある。発注ミスや納期の遅れが命取りとなる状況の中、営業担当者は現場に足しげく通い、地震発生から納品完了まで3年近くもの間、最新の状況をはじめとした現場の声をメーカーに連携し続けた。
![]()
地域と未来へのメッセージ
メーカー・建設会社双方の要望が100%通らないこともある中で、間に入って調整を続け、最終的に1号ふ頭の岸壁に納めた鋼矢板は総延長数百メートルにも及んだ。
地域の要である相馬港が2年連続で甚大な被害を受けるという、緊急事態の中で立ち上がった復旧プロジェクト。
そこに“鉄の力”を呼び込むという役割を全うできたことは、私たちの誇りとなっている。
阿武隈山地に吹く風を、未来のエネルギーに
事例紹介projects 02
- 葛尾風力発電所建設工事
- 生コンクリート(東北レミコン)
挑戦の始まり
東日本大震災後、福島県は再生可能エネルギーに重点を置くようになった。その流れもあり、浜通り(福島県沿岸部)の西側に位置する阿武隈山地には、100基前後の風力発電が建設されている。
標高数百メートルの阿武隈山地。その尾根沿いに新たに建設する5基の風力発電の基礎部分に、生コンクリートを届けるのが今回の仕事。
どこの工場からも遠い山間部へ、複数の工場から同じタイミングで生コンクリートを運ぶという“共同”プロジェクトが始まった。
![]()
困難と克服
巨大な風力発電を支える基礎部分には、高品質の生コンクリートが大量に必要となる。今回、アジテータ車で延べ100台以上の生コンクリートを、たった1日で運ぶ必要があった。
近くの現場であれば自社の車両のみで何往復もして運ぶことが可能だが、山間部のため、1回の配送でも往復2時間以上かかる。そのため、複数社で協働し、より多くのアジテータ車を駆使して届けることとなった。
複数社が1つの構造物のために協力して同じ資材を運ぶというのは、例えるなら巨人と阪神が一緒のチームでプレーするような特殊な状況。それほどまでに、このミッションは稀有な挑戦だった。
生コンクリートは、その日の天候や気温にも品質を左右される繊細な材料だ。一番いい状態で現場に届けるために、どんな準備をし、どんな配合設計で持っていくのか。距離が長くなればなるほど品質管理の難易度は上がる。
さらに、同じ構造物の基礎に、異なる2社の生コンクリートを一緒に打設するという特殊なケースである。「2社の製品を混ぜても正常に硬化して必要な強度が出るか」を事前試験して確認するなど、普段以上の入念な準備で対応した。
![]()
挑戦の意義と未来
同業他社と協力して同時に生コンクリートを届けるプロジェクトは、数年に1度の非常に珍しい機会。
工場同士が利害関係を抜きにして協力できる関係を、結果として築くことができたが、この起点には“お互いの営業メンバーを通じた相手への信頼”というものがあったように思う。
本プロジェクトでの協業は、新商品の開発にもつながった。「リサイクルコンクリートブロック」は、一緒に協力した会社から余った生コンクリートの活用方法を教えてもらい、私たちの新商品となったものだ。
ひとつの大きな挑戦から始まった関係性は、プロジェクトの達成というゴールを超えて、これからも新たな未来を生み出していくだろう。
見えないインフラが支える、農業の未来
事例紹介projects 03
- 復興基盤総合整備工事
- 農業パイプライン用管材(クボタグループほか)
プロジェクトの始まりと背景
東日本大震災で著しい被害を受けた福島県の農業。
その円滑な復興に不可欠なのが、パイプラインの設置である。農業用水を送排水するため、地中にパイプラインを埋設する建設工事。地方の基盤となる一次産業を守る、大切な事業だ。
農地は数年間、人の手が入らずに放置されると荒れてしまう。そうした土地を再生させるため、被災した各地区で継続して実施されている復興プロジェクトである。
東北商事は、クボタグループのパイプライン用管材をメインとして、様々な材質の製品を取り扱っている。
今回のようなプロジェクトにおいては、県が発注する復興工事を請け負う建設会社に対して営業をかけていく。営業メンバーは、公開されている工事発注見通し資料をもとにメーカーサイドと方針を共有する。そして、お客様とのつながりを活かして現場情報を拾い上げながら全体像をつかまえて、自分たちにできることを模索していく。
![]()
パイプライン事業への挑戦の意義
パイプライン事業は、工区によって数kmにも及ぶ材料を扱うような大規模案件もある。
さらに、2025年度においても過去最高水準の工事発注量となる見通しであり、地域におけるニーズは非常に高い。複数の案件が同時に動く日々の中、営業メンバーはそれぞれが関わるプロジェクトのために奔走している。
農業復興を根幹で支える建設資材。工事期間中しか見えないパイプラインだが、作物を生産するための土台として地中で力を発揮していく。
長い復興の道のりにおいて、地域の原動力となる農業の再生は、欠かすことのできないものである。
農地を蘇らせる過程において、「メーカーが製造する資材の力」と「地域の人びとの力」をむすんで、新たな出発を見届けること。
それこそが、東北商事がこの事業に関わる目標であり、私たちに達成感をもたらしてくれるものでもある。
![]()